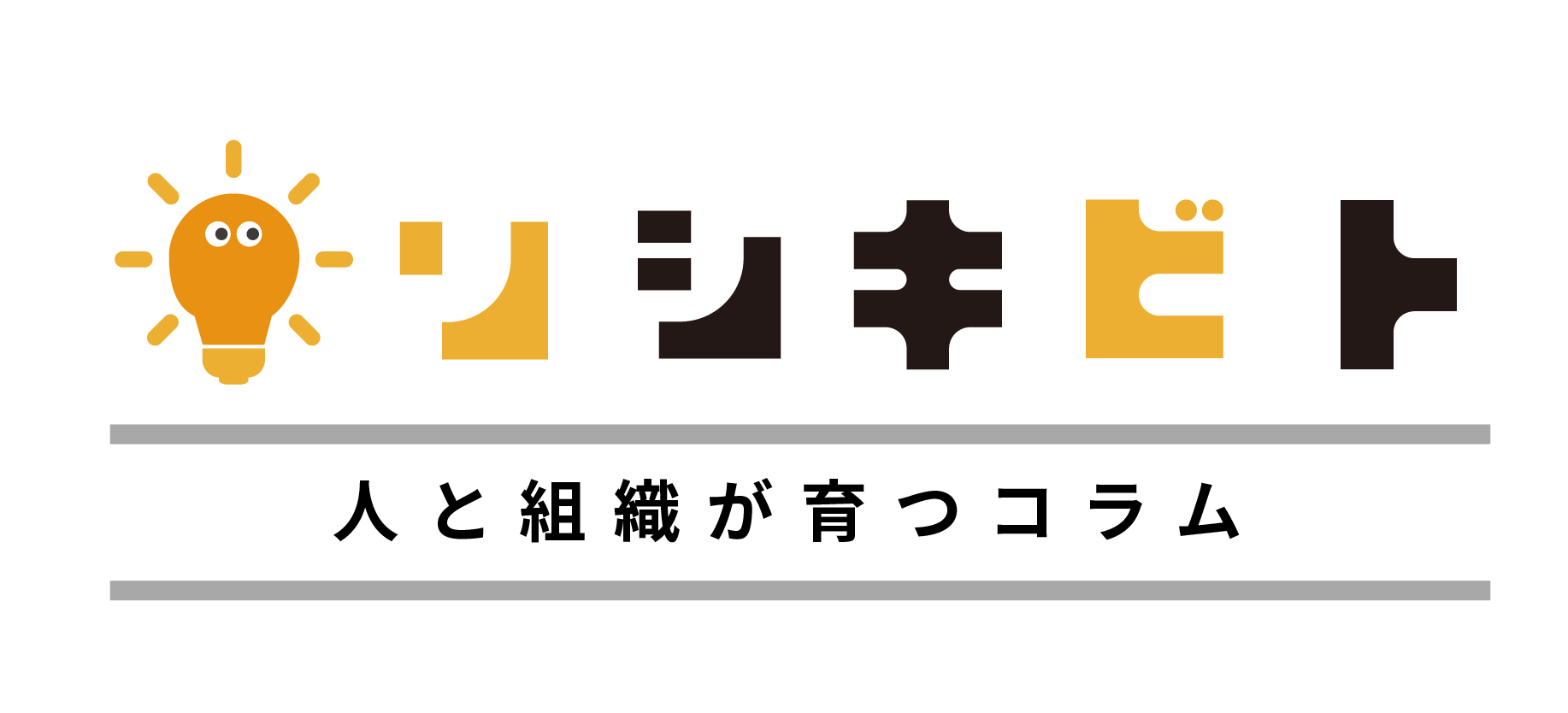社員のモチベーションを向上させる施策は、組織を活性化する上で必要な視点です。しかし、「モチベーションが上がらない」「仕事に対するやる気が低下し行動を起こさない」など、悩みを抱える企業が多いのも事実でしょう。
では、どうすればモチベーションを向上させることができるのでしょうか。本記事では、社員のモチベーションを上げる具体的な方法を解説すると共に、モチベーションアップに取り組む企業の事例を紹介します。
【本記事で得られる情報】
・モチベーションの意味や種類
・モチベーションアップが必要な理由
・モチベーションが低下する原因
・モチベーションが低下するデメリット
・モチベーションを向上させる方法
・モチベーションの向上に取り組む企業の事例
モチベーションとは?意味を解説

私たちが日常良く使う「モチベーション」という言葉。そもそもモチベーションとは、どのような意味なのでしょうか。はじめに、モチベーションの意味や種類について、あらためて整理しておきましょう。
【モチベーションの意味】
モチベーションとは、目標や目的に向かって行動を起こし、その行動を維持するために必要な動機となる“内的な原動力”のこと。
企業活動においては、仕事に対する社員の「やる気」や「意欲」を表す言葉として使われます。
モチベーション(motivation)は、「motive:動機・誘因・動因」と「action:行動・活動・行為」から成り立つ言葉であり、本来「行動するための動機」を意味します。
つまりモチベーションとは、目標や目的の達成を目指し、成果を得るために必要となる「動機づけ」を意味する言葉なのです。
関連記事:モチベーションの3要素
モチベーションの種類

モチベーションには、2つの種類があります。
【モチベーションの種類】
・外発的モチベーション
・内発的モチベーション
ここでは、この2つのモチベーションについて解説します。
外発的モチベーション
外発的モチベーションとは、人の内側(内面)ではなく外側からの刺激(動機・要因)によって沸き起こるモチベーションのことです。具体例をあげましょう。
【外発的モチベーションの具体例】
・お金を稼ぐために仕事をする
・給与アップを目指し働く
・昇進や昇格を目標に頑張る
・営業目標をクリアするために行動する
・生活のために仕事を続ける
こういった、目的意識(外からの刺激)を行動の原動力とするのが外発的モチベーションです。
外発的モチベーションは、他者からの「称賛」や「承認」、金銭的あるいは名誉的な「欲求」、望まないこと(罰)を避けたいという「意識」が刺激となります。そのため、比較的簡単に向上させることができる反面、維持することが難しいのが特徴です。
内発的モチベーション
一方、内発的モチベーションとは、外側ではなく人の内側(内面)からの刺激によって沸き起こるモチベーションのことです。具体例をあげてみます。
【内発的モチベーションの具体例】
・将来に向けて資格を取得する
・仲間の力になりたい思いから先頭に立つ
・会社に貢献したい一心でアイデアを考える
・役に立ちたい思いで行動する
・時間を忘れて好きなことに没頭する
このような、内面の意識(中からの刺激)を行動の原動力とするのが内発的モチベーションです。
内発的モチベーションは、自らの意志や責任で行動できる「主体性」、自分から積極的に働きかける「能動的」姿勢、自分の意志で物事を進める「自発性」が刺激となります。そのため、モチベーションを維持しやすい反面、向上させることが難しいのが特徴です。
関連記事:モチベーション・マネジメントとは?
社員のモチベーションをアップさせる必要性

ここでは、社員のモチベーションをアップさせる必要性について解説します。まず、モチベーションが高い社員の特徴を整理してみましょう。
【モチベーションが高い社員の特徴】
・新しい仕事や困難な業務にも積極的に挑戦する
・簡単に諦めることなく粘り強く仕事に取り組む
・仕事に対する集中力が高くその状態を維持できる
・周りの社員にも積極的に働きかけ組織を活性化させる
・多様な意見を受け入れ調整することをいとわない
モチベーションの高い社員が、企業に与える影響は絶大です。社員一人ひとりのモチベーションがアップし、成果を上げれば、企業の業績もアップするでしょう。社員の成長意欲が高まれば、企業の成長も期待できるのです。
社員のモチベーションと企業の業績・成長性は、密接に関係しています。企業の価値は、モチベーションの高い社員から生み出されるといっても過言ではありません。このような理由から、社員のモチベーションをアップさせる取り組みが求められているのです。
関連記事:組織を活性化するには
社員のモチベーションを下げる原因

社員の高いモチベーションは、企業にとって必要不可欠です。にもかかわらず、なぜ低下するのでしょうか。ここでは、その原因を考察します。
【社員のモチベーションを下げる原因】
・人間関係によるストレス
・仕事や業務に対する不満
・評価に関する不満
・将来に向けての不安
ひとつずつ詳しく解説しましょう。
人間関係によるストレス
人間関係によるストレスは、社員のモチベーションを低下させる大きな原因です。上司との関係が良好でない場合、業務に集中できず会社への貢献意欲も減少します。
社員同士や部署間のコミュケーションがうまくいかない職場は、風通しが悪いばかりか心理的安全性が担保できずに、自由闊達な意見交換ができなくなります。こうなっては、社員のモチベーションは下がる一方でしょう。このように、人間関係によるストレスは、社員のモチベーションに大きな影響を与えるのです。
仕事や業務に対する不満
自分の仕事や業務に不満を抱えていては、モチベーションが下がるのも当然です。「自分が望んだ業務とは違う」「ミスマッチだ」「目標管理が厳しすぎる」といった状況の中で、モチベーションが次第に失われていきます。
この状態では、仕事に向き合う前向きな姿勢も失われて、「意欲」や「やる気」がなくなってしまいます。仕事や業務に対する不満は、モチベーションの低下に直結する大きな原因です。さらに、こういった状態を「把握しようとしない」「改善しない」ことが、さらなるモチベーションの低下を招いてしまうのです。
評価に関する不満
社員が「自分の頑張りを正当に評価してくれない」と感じれば、モチベーションは低下してしまいます。評価に関する不満も、社員のモチベーションを下げる原因のひとつです。
また、待遇面での不満もモチベーションを下げてしまいます。給与や福利厚生をいかに充実させるのかは、社員のモチベーションを維持する大きな課題でしょう。その他、残業の多さや休日の少なさ、体力的にハードな労働環境も、社員のモチベーションを下げる原因となります。
将来に向けての不安
将来に向けての不安も、社員のモチベーションを下げる原因です。「将来のキャリアプランが描けない」「今後の目標が見つからない」「この会社にいていいのか」など、将来に対する不安は、働く意味づけさえ見失わせる可能性があるのです。
また、会社の理念やビジョン、パーパスに対する違和感も、社員のモチベーションを左右する要因になります。違和感を抱く社員が増えると、組織全体の活力が失われてしまう可能性すらあるのです。
関連記事:職場のメンタルヘルスケア
社員のモチベーション低下で起こること

では、社員のモチベーションが低下した場合に起こるデメリットを考察しましょう。
【モチベーション低下のデメリット】
・生産性が低下する
・ブランド力が下がる
・周りの社員に悪影響をもたらす
・離職率が増加する
詳しく見ていきましょう。
生産性が低下する
社員のモチベーションが低下した場合、企業の生産性も低下します。先に述べたように、社員のモチベーションと企業の業績は密接に関係しています。優秀な社員が多くいたとしても、モチベーションが低ければ効率的に価値を生み出すことができません。
一般的に、モチベーションの高い社員に対して、低い社員の生産性は3割以下と言われています。このように、モチベーションの「高い低い」は、企業が生み出す価値に大きな影響を与えるのです。
ブランド力が下がる
社員のモチベーションが低下し生産性が下がれば、顧客満足度が低下しブランド力も下がってしまいます。さらに、ブランド力を回復しようとする意欲すら失くしてしまう可能性もあるのです。
モチベーションの低下は、企業活動を停滞させてしまう危険性をはらんでいます。モチベーションの在り方が対外的な評価を左右し、企業のブランド力にも影響することを認識しておくべきでしょう。
周りの社員に悪影響をもたらす
社員のモチベーション低下は、周りの社員にまで悪影響をもたらします。生産性が上がらないツケは、周りの社員に回ってきます。仕事量の増加をはじめ、進捗も滞るでしょう。
こうなると、周りの社員がストレス抱えてしまい、会社に対する不満を募らせることになりかねません。不満が蔓延すれば、職場全体の雰囲気も悪くなります。社員一人のモチベーションの低下が、周りの社員にも悪影響をもたらす。認識しておきたい懸念事項です。
離職率が増加する
モチベーションの低い社員が多い会社は、離職率が増加する傾向があります。モチベーションが低い社員は、仕事に集中できないためミスが多くなりがちです。次第に、仕事に対する「やりがい」や「楽しさ」もなくなっていきます。
こうなっては、離職を選択する可能性が高くなります。人材獲得競争が激しい社会において、社員の離職は大きな問題です。離職率の増加はさらに、人材を補強する採用コストを増加させると共に、人材の育成コストも増加させる悪循環にもつながってしまうのです。
関連記事:社員の離職防止対策
社員のモチベーションの上げ方

見てきたように、モチベーションの低下は企業に大きな影響を与えます。社員のモチベーションを上げることは、業績を左右する大きな課題です。ここでは、社員のモチベーションの上げ方を見ていきましょう。
【社員のモチベーションを上げる方法】
・モチベーション理論を意識する
・理念、ビジョン、パーパスを明確にする
・職場環境を改善する
・キャリア形成を支援する
・エンゲージメントサーベイを実施する
詳しく解説します。
モチベーション理論を意識する
モチベーション理論とは、心理学に基づき人の行動を動機づける要因を探り、その行動がどのように「促され」「方向性を決め」「維持される」のかを紐解くものです。社員のモチベーションを向上させるために、この理論を活用します。
ここでは、2つモチベーション理論を紹介しましょう。
マズローの欲求段階説
欲求段階説とは、アメリカの心理学者マズローが提示した、人の欲求を5段階に階層化したものです。「人の欲求は、低次から順に満たされていき、ひとつの段階が満たされると、もう1段階上を求める」と説いています。5段階とは、低次から順に「生理的欲求→安全欲求→社会的欲求→承認欲求→自己実現欲求」です。
これを会社にあてはめると、第1段階の生理的欲求(安心できる給与を得たい)をまず満たし、次の段階の安全欲求(健康で働きたい)を満たす。そしてまた、次の段階を満たしていくのです。社員のモチベーションを上げるには、まず低次の欲求から満たしていく。マズローの欲求段階説は、それを教えてくれます。
衛生要因と動機づけ要因
衛生要因とは、仕事の「不満」にかかわる要因です。一方、動機づけ要因とは、仕事の「満足度」にかかわる要因です。アメリカの臨床心理学者ハーズバーグによって提唱されました。
不満を解消するには、衛生要因を満たす必要があります。また、満足度を高めるには動機づけ要因を満たす必要があります。つまり、両方を同時に満たすことが重要なのです。それぞれの具体例をあげます。
衛生要因
・給与、労働条件、福利厚生、経営方針、人事労務体制、人間関係、仕事の安全性など
動機づけ要因
・達成感、仕事内容、周囲の承認、責任、昇進昇格、裁量権、成長機会など
衛生要因と動機づけ要因を満たすことで、社員のモチベーションアップに努めます。
理念・ビジョン・パーパスを明確にする
会社の「理念・ビジョン・パーパス」を明確にし共感を得ることは、社員のモチベーションアップにつながります。なぜなら、理念・ビジョン・パーパスが十分に共有されている会社では、社員同士の一体感や仕事に対する誇り、会社への信頼感が高まるからです。
理念・ビジョン・パーパスを明確にし、仕事との関連性、また社会的な役割を全社的に共有することで、社員のモチベーションを高めていきます。
職場環境を改善する
前項で述べた、マズローの欲求段階説、衛生要因と動機づけ要因を意識しながら職場環境の改善を図ります。具体例をあげましょう。
・給与や待遇、福利厚生の見直し
・残業や休日出勤の削減
・有給休暇が取得しやすい環境整備
・公平な評価制度や人事制度の確立
・金銭を伴わないインセンティブの導入
・役割期待の明確化
・社内コミュニケーションの活性化
・チャレンジできる、称賛する社内文化の醸成
こういった職場環境の改善が、社員のモチベーションを上げていくのです。
キャリア形成を支援する
今、働く個人と組織の関係性の在り方が変わろうとしています。それは、「相互依存」から「自立対等」な関係性への変化です。人生100年時代。社員はキャリア形成を続け、企業はそれを支援するパートナーとしての関係性を構築する必要性が高まっています。
その環境を整えることが、社員のモチベーションを向上させるでしょう。これからは、企業が社員と伴走しながらキャリア形成をバックアップしていく支援の在り方が求められています。
エンゲージメントサーベイを実施する
エンゲージメントサーベイとは、社員と企業の「結びつき」の強さを可視化する調査のことです。仕事や企業と向き合う、社員の「思考面・情緒面・行動面」における関与の度合いを数値化します。調査結果から見えてきた課題を改善プランに落とし込むことで、社員のモチベーションアップ、企業の活性化を目指します。
様々な改善に取り組むには、まず社員と企業の状況を把握することが何よりも重要です。エンゲージメントサーベイは、社員と企業の状況把握に効果を発揮します。
関連記事:エンゲージメントサーベイとは?
社員のモチベーションを上げる施策~向上に取り組む企業の事例

では、社員のモチベーションアップに取り組む企業の具体的な事例を紹介します。
サイボウズ株式会社
サイボウズ株式会社は、「育自分休暇」制度を導入しています。35歳以下を対象とし、転職や留学を通して自分を成長させたい社員は、最長で6年まで会社への復帰が可能です。
「職場復帰が可能なので、スキルアップにチャレンジできる」と社員にも好評。社員のモチベーションアップとスキルアップを兼ねた取り組みとなっています。
株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントは、社員の休暇制度として「リフレッシュ休暇 休んでファイブ」を導入しています。この制度は、社員が自発的にチャレンジできるように、心と体をリフレッシュしてもらうことが目的です。
入社3年目からの社員は、毎年5日間の「リフレッシュ休暇 休んでファイブ」の取得が可能。周りを気にせずに休みを取れる環境を整え、仕事に対するモチベーションの維持を目指しています。
ザ・リッツ・カールトン
ホテルを世界中で展開する「ザ・リッツ・カールトン」は、社員同士のコミュニケーションを活性化させるため、「ファーストクラス・カード」を導入しています。「ファーストクラス・カード」とは、仕事を手伝ってくれた社員に対して、感謝を伝える手渡しカードのことです。
「ファーストクラス・カード」は、人事評価の参考にもされています。社員同士が称賛しあう文化を根づかせることで、褒められた社員のモチベーションを高めることに成功しています。
関連記事:従業員満足度が高い職場環境とは?
最後に

今回は、社員のモチベーションを上げる方法を解説しました。社員のモチベーションを向上させるには、まず社員と企業の状況を把握することが重要です。
そのためには、エンゲージメントサーベイを実施し、社員と企業の現在の状況を定量的かつ定性的に測定する必要があります。その調査結果を基に、職場環境を改善していくことが、社員のモチベーションアップにつながるのです。
リアルワン株式会社は、調査・評価の専門会社です。科学的根拠に基づく信頼性の高い「エンゲージメントサーベイ」で、従業員と組織の成長をサポートします。モチベーションの高い組織を作るには、まず現在の状況把握から。リアルワンが提供するエンゲージメントサーベイを、ぜひご活用ください。