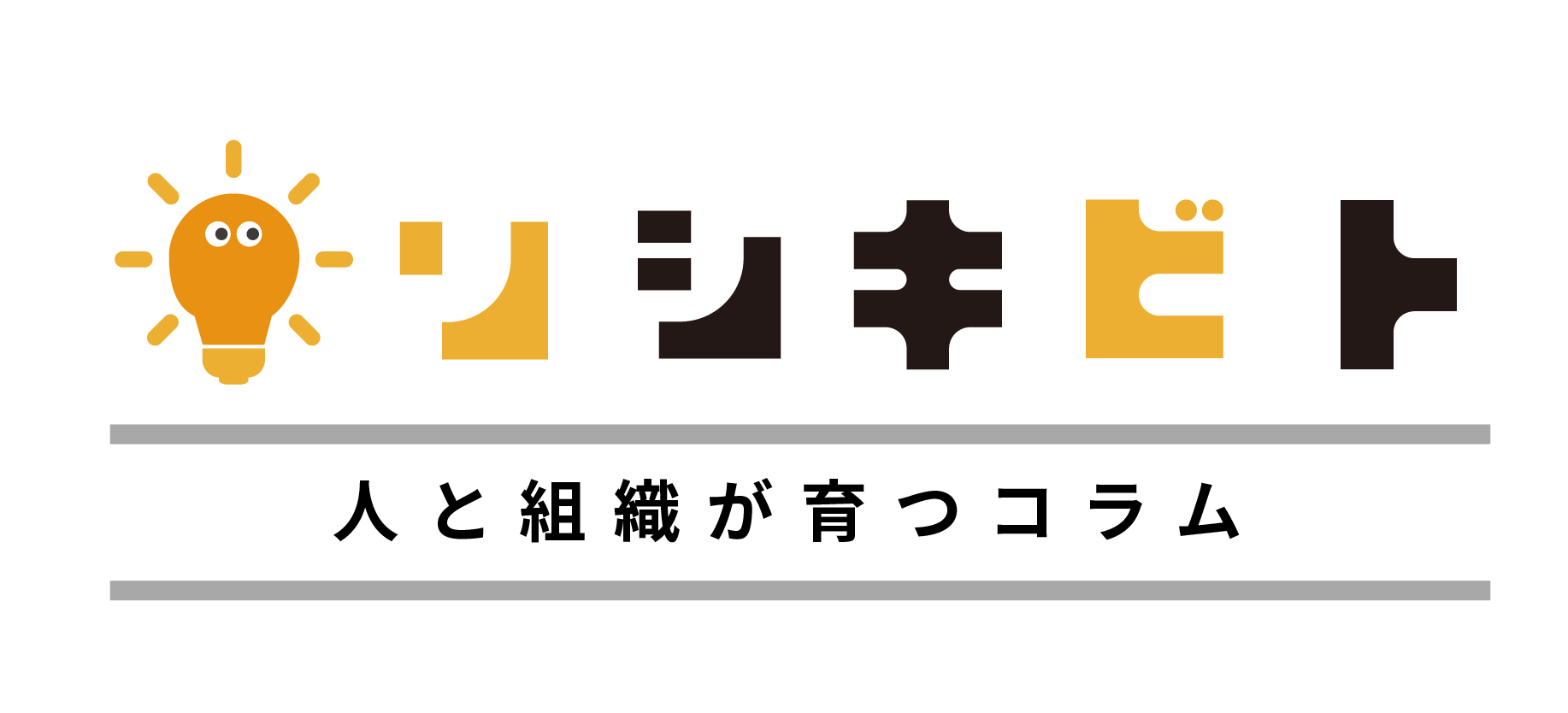仕事に向き合う「やる気」「意欲」を表す「モチベーション=動機づけ」は、目標管理や生産性の向上に関わる大きな要因です。しかし、「仕事に対するモチベーションが低い」「職場のモチベーションが上がらない」など、社員のモチベーションに課題を抱える企業様も少なくないでしょう。
そこで今回は、モチベーションが下がる職場や低い社員の特徴を紹介しながら、モチベーションが向上しない原因を分析。どうしたらモチベーションを向上させることができるのか、その方法を解説します。
【本記事で得られる情報】
・モチベーションが向上しない原因
・モチベーションが下がる職場の特徴
・モチベーションが低い社員の特徴
・モチベーションが高い社員の特徴
・モチベーションマネジメントの意味
・モチベーションを向上させる方法
・モチベーションを測定する方法
モチベーションが下がる職場とは?

モチベーションとは、行動を起こし、その行動を維持する動機づけのことです。企業における社員のモチベーションは、生産性や離職率にも関わる重要な要因です。
では、この重要な社員のモチベーションが下がる職場とは、どのような職場なのでしょうか。はじめに、モチベーションが下がる職場の特徴を見ていきましょう。
【モチベーションが下がる職場の特徴】
・仕事に達成感や満足感がない
・職場の人間関係が良好ではない
・給与が低すぎる
・残業が多い
詳しく解説します。
仕事に達成感や満足感がない
同じ仕事を毎日繰り返しているとマンネリ化してしまい、仕事に対する達成感や満足感がなくなってしまうものです。加えて、成果が目に見え難かったり、顧客からの反応が伝わり難かったりする場合、その傾向がより強くなります。
こういった環境では、モチベーションが次第に失われていきます。達成感や満足感は、社員のモチベーションに関わる大きな要素です。「何のために仕事をしているのか分からない」「仕事に意義を見出せない」など、ネガティブな感情を持つ社員が多くなると、組織自体の熱量までが失われてしまうのです。
職場の人間関係が良好ではない
社員のモチベーションが下がる職場の多くは、人間関係が良好ではありません。仕事が忙しくても、疲れがたまっても、人間関係に問題がなければ、やる気や頑張りで多少はカバーできます。しかし、人間関係が良好ではない場合、それができなくなるのです。
人間関係とモチベーションは、密接に関係しています。良好な関係性、活発なコミュニケーション、称賛し合える文化は、社員のモチベーションを向上させ、組織全体のパフォーマンスを向上させます。日頃から、人間関係がモチベーションに与える影響を考慮し、風通しの良い職場環境を整えることが重要です。
給与が低すぎる
社員のモチベーションを左右する要素には、様々なものがあります。給与も、そのひとつです。給与は、仕事に向き合う社員のモチベーションに大きく関わります。給与が低すぎては、モチベーションを著しく下げてしまうことになるのです。
成果に見合った給与を得るのは、働く上での基本です。時には、役割以上の仕事を担当することもあるでしょう。評価基準を明確にして、適正な給与水準で社員を労うことが求められています。
残業が多い
残業が多いことも、社員のモチベーションを下げてしまいます。長時間労働は、ストレスを蓄積させます。ストレスが溜まっては、モチベーションが下がるばかりか健康にまで悪影響を与えかねません。
仕事量が多くてもモチベーションが高ければ、処理も早く生産性は上がるものです。しかし、残業が多く、しかも深夜にまで及ぶような残業が続けば、十分な睡眠をとることもできず体調不良につながります。
必要な残業も、中にはあるでしょう。しかし、残業が多いのは、やはり問題です。社員の健康とモチベーションには、密接な関係があります。業務の効率化に取り組み、社員の健康とモチベーションの維持に努めたいものです。
関連記事:モチベーションの低下で起こることとは?
社員のモチベーションが低い原因

では、モチベーションが低い原因を、社員のサイドから考察してみましょう。
【社員のモチベーションが低い原因】
・目的意識が欠如している
・自分の裁量で職務を遂行できない
・評価基準に不満を持っている
・心理的安全性に不安を持っている
ひとつずつ解説します。
目的意識が欠如している
目的意識が欠如している社員は、モチベーションが低くなります。なぜなら、「やらされ感」の中で仕事をしているからです。「目的が分からない」「言われたからやっている」「ゴールが見えない」といった思いを持ちながら仕事にあたると、「やらされ感」が強くなりやる気が低下してしまいます。
大切なことは、仕事の意味や必要性、企業が求める成果を明確にし、社員と共有することです。仕事の目的が分かれば意識が変わり、仕事に取り組む姿勢も変わります。同時に、モチベーションもプラスの方向に変化していくのです。
自分の裁量で職務を遂行できない
自分の裁量で職務を遂行できないことも、社員のモチベーションを下げる原因になります。仕事は、判断の連続です。仕事を進めるにあたって、社員は日々何らかの判断を求められています。その判断に関して、いちいち上司に伺いを立てなければならない状況では、社員のモチベーションが上がらないのも仕方ないでしょう。
「エドワード・L・デシ」は、モチベーションを理論化した自己決定論において、「自律的な決定こそがモチベーションの向上につながる」と述べています。逆に言うと、自分自身で決定できなければ、モチベーションが低下するということです。
裁量権には、メリットデメリットがあるのは事実です。しかし、社員に適度の裁量権を与えることが、モチベーションの向上につながるということを認識しておくべきでしょう。
評価基準に不満を持っている
評価に対する不満は、モチベーションを低下させる大きな原因です。頑張りが、「どう評価されているのか分からない」「正当に評価されていない」など、評価基準に不満を持っていると、モチベーションは下がっていくばかりです。
明確な評価基準は、社員のやる気を喚起します。また、仕事や組織に対する「満足度・エンゲージメント」にも関わる重要な要素です。公平で透明性の高い評価基準を構築し、ビジネス環境の変化に応じて随時見直していく柔軟性が求められています。
心理的安全性に不安を持っている
心理的安全性とは、仕事や人間関係を意識することなく、自由闊達に意見や考え方を言葉にできることです。心理的安全性が担保された組織は、立場や年齢を気にせず、すべての社員の発言が尊重され受容される環境が整っています。
この心理的安全性に不安があっては、言いたいことが言えず、言っても受け入れてもらえず、息が詰まってしまいます。これでは、モチベーションが上がるはずもありません。心理的安全性は、社員同士の信頼関係があってこそ作れるものです。モチベーションを向上させるためにも、心理的安全性の確保に努めたいものです。
関連記事:モチベーションをアップさせる必要性
モチベーションが低い社員と高い社員の特徴

モチベーションが下がる職場の特徴、そして社員のモチベーションが低い原因を見てきました。ここで、モチベーションが低い社員と高い社員の特徴を整理しておきましょう。
モチベーションが低い社員の特徴
モチベーションが低い社員には、次のような特徴が見られます。
【モチベーションが低い社員の特徴】
・仕事の生産性が低い
・チャレンジ精神を持てない
・チームに溶け込めず孤立しがちである
・満足度やエンゲージメントが低い
・中長期的な視点を持てずに離職を繰り返す
モチベーションが低い社員は、「やらされ感」が強く積極性がないため、仕事の生産性が低くなります。また、仕事に向き合う姿勢も後ろ向きで、チャレンジ精神を持てません。さらに、コミュニケーションが少ないため、チームに溶け込めず孤立しがちです。
こうなっては、満足度やエンゲージメントも低くなってしまいます。次第に、仕事は単なる「作業」になっていき、キャリアに対する中長期的な視点を持てずに離職を繰り返す、悪循環に陥ってしまうのです。
モチベーションが高い社員の特徴
では、モチベーションが高い社員には、どのような特徴があるのでしょうか。
【モチベーションが高い社員の特徴】
・主体的かつ自発的である
・効率的で生産性が高い
・周囲を巻き込みチームを引っ張る力がある
・自らゴールを設定しキャリアプランを描ける
・満足度やエンゲージメントが高い
モチベーションが高い社員は、主体的かつ自発的です。仕事に取り組む集中力が高く、何事も効率的に処理していきます。当然、生産性は高くなるでしょう。その積極的な姿勢は、周囲を巻き込みチームを引っ張る力となります。
また、モチベーションが高い社員は、自分のキャリアを中長期的に俯瞰するこができます。自らゴールを設定し、ゴールから逆算したキャリアプランを描けるのです。
このように、モチベーションが高い社員は、キャリアに対するコミットメントの度合いが高いのが特徴です。そしてそれは、満足度やエンゲージメントも高いということを示しているのです。
関連記事:モチベーションが重要な理由
モチベーションマネジメントの必要性

見てきたように、社員のモチベーションは企業にとって不可欠の要因です。今、このモチベーションを企業が管理し、向上させていく取り組み「モチベーションマネジメント」が注目されています。ここでは、モチベーションマネジメントについて解説します。
モチベーションマネジメントとは?
モチベーションマネジメントとは、社員のモチベーションを企業が管理し、高い動機づけで仕事に向き合えるよう環境を整える取り組みのことです。「2つのモチベーション」に影響を与える意識に働きかけ、より高いモチベーションを引き出すマネジメント手法を指します。
2つのモチベーションとは、次の通りです。
【外発的モチベーション】
他者からの称賛や承認、金銭的・名誉的な欲求、望まないことを避けたい思いといった、外側からの刺激によって生まれるモチベーション
【内発的モチベーション】
自分の意志や責任で行動できる主体性や自発性、能動的姿勢といった、内面からの刺激によって生まれるモチベーション
この2つのモチベーションを管理し、維持する取り組みがモチベーションマネジメントです。
モチベーションマネジメントの重要性
モチベーションマネジメントは、「モチベーションが下がる職場、低い社員」に対する有効な解決策のひとつです。ただ、モチベーションマネジメントには、それ以上の意味があります。
人口減少社会となり、労働力の低下は避けられません。人材獲得競争は、さらに激しさを増していくでしょう。これからの企業には、限られた人材の中でパフォーマンスを最大化させていく取り組みが求められています。
この大きな課題をクリアする方法は、様々でしょう。テクノロジーを活用するのも、そのひとつです。しかし、そこにはやはり社員が必要です。その社員の「やる気・意欲」を決定づけるのが、モチベーションに他なりません。最先端テクノロジーの効果も、それを扱う社員のチベーション次第なのです。
モチベーションは、社員のパフォーマンス、そして企業の成長性に大きく関わります。企業は、この極めて重要なモチベーションを管理し、社員に対して何らかの働きかけを行うことが必要不可欠になっているのです。
この働きかけがモチベーションマネジメントであり、社員と組織のパフォーマンスを最大化させる取り組みとして、その重要性が増しているのです。
社員のモチベーションを管理し上げる方法

では、社員のモチベーションをどのように管理し、向上させていけばよいのでしょうか。ここでは、その方法を解説します。
【社員のモチベーションを管理し上げる方法】
・社員のモチベーションを把握する
・社員の意見を洗い出す
・職場の課題を改善する
・成功体験を積む機会を作る
詳しく見ていきましょう。
社員のモチベーションを把握する
モチベーションを管理するためには、社員のモチベーションを把握する必要があります。モチベーションは、常に一定で安定している訳ではありません。様々な要素で変化しています。モチベーションマネジメントの最初のステップは、社員のモチベーションを把握することにあります。
社員のモチベーションを把握する方法としては、チームミーティングを行ったり、1on1ミーティングを実施したりするのが効果的です。社内コミュニケーションを活性化させることは、社員のモチベーションを把握する機会になります。また、後述するサーベイ(調査・測定)を導入すれば、社員のモチベーションを数値として可視化することも可能です。
社員の意見を洗い出す
モチベーションに影響を与える要素を特定するには、社員の意見を洗い出す必要があります。この意見の洗い出しも、モチベーションマネジメントに取り組む際の欠かせないステップになります。社員のモチベーションを左右する要素を理解するには、社員の意見に耳を傾ける必要があるのです。
社員の意見を洗い出すには、双方向のコミュニケーションが有効です。仕事のどこに不満を持ち、ストレスを感じているのか。前向きに仕事に取り組むためには、何が必要なのか。社員の意見を洗い出し、モチベーションマネジメントに落とし込んでいきます。この意見の洗い出しにも、後述するサーベイ(調査・測定)が効果的です。
職場の課題を改善する
社員のモチベーションを把握し、意見の洗い出しができれば、職場の課題が見えてきます。次のステップは、職場の課題を改善することです。具体例をあげましょう。
・給与や待遇、福利厚生を見直す
・仕事量の偏りをなくし、残業や休日出勤を削減する
・有給休暇を取得しやすい社内文化を作る
・役割に対する期待値を明確化する
・公平で透明性の高い評価基準や人事制度を構築する
・「理念・ビジョン・パーパス」の浸透を図る
・社内コミュニケーションを活性化させる
・誰もがチャレンジができて、失敗しても受け入れる環境を整備する
このように、職場の課題を改善することが社員のモチベーションを向上させていくのです。
成功体験を積む機会を作る
成功体験を積み上げることで、モチベーションは向上していきます。成功体験は、「自己効力感(自分はできるという感覚)」を高めます。社員のモチベーションを上げるため、成功体験を積む機会を作りましょう。
意識すべきは、「スモールステップ」です。小さな成功体験の積み重ねが自己効力感を高め、モチベーションを向上させます。スモールステップは、アメリカの心理学者スキナーが提唱した、「プログラム学習」の原理のひとつです。
ポイントは、大きな目標ではなく「手が届く目標」を設定すること。具体的には、次のような目標です。
・できないことの分析から始める
・できることから手を付けていく
・目標達成に向けて新規顧客を10件リストアップする
・1日1回はSNSで新商品の発信を行う
・ミーティングで必ず1回は発言する
・月に2回は改善提案を行う
・会議に集中するため議事録係になる
まずは手が届く目標を設定し、それをクリアしたら少しずつハードルを上げていきます。この繰り返しが社員の自己効力感を高め、モチベーションの向上につながっていくのです。
モチベーションを測定する方法~サーベイ(調査・測定)を実施する

モチベーションマネジメントは、社員のモチベーションを把握することから始まります。また、社員の意見を洗い出すことも重要です。それには、ミーティングや双方向のコミュニケーションが有効であるのは、先に述べた通りです。
それに加えて、「サーベイ(調査・測定)」を実施すれば、社員の意見を吸い上げつつモチベーションを可視化することができます。ここでは、モチベーションの測定に効果的な2つのサーベイについて解説します。
従業員満足度調査(ES調査)
従業員満足度調査(ES調査)とは、組織における従業員の満足度を測定するサーベイのことです。職場の「働きやすさ・人間関係・給与・福利厚生・ワークライフバランス」といった様々な項目に関してアンケート調査を行い、従業員の満足度を数値として可視化します。
従業員満足度の英訳、「Employee Satisfaction」の頭文字をとって「ES調査」とも呼ばれています。従業員満足度調査(ES調査)は、従業員と組織の「今の状態」を可視化するサーベイとして、モチベーションの測定にも効果的です。
エンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイとは、従業員と企業の「結びつき」の強さを測定し、従業員と企業の関係性や仕事に対するコミットメントの度合いを数値化するサーベイのことです。エンゲージメントとは、仕事に取り組み、企業と向き合う従業員の「思考面・情緒面・行動面」におけるコミットメントの度合いです。
従業員の愛社精神を表すエンゲージメントと、サーベイを組み合わせてエンゲージメントサーベイと呼ばれています。エンゲージメントサーベイは、従業員のエンゲージメントを客観的に可視化するサーベイとして、モチベーションの測定にも効果的です。
従業員満足度調査(ES調査)とエンゲージメントサーベイは、従業員の意見を洗い出すことで、組織の状態、そしてモチベーションを客観的に可視化します。従業員のモチベーションを把握するため、ぜひ有効活用したい施策です。
関連記事:従業員満足度調査(ES調査)とエンゲージメントサーベイの違いとは?
最後に

今回は、モチベーションが下がる職場と低い社員の特徴を紹介しながら、モチベーションが低い原因、そしてモチベーションの上げ方を解説しました。モチベーションを向上させるには、モチベーションマネジメントに取り組むことが求められます。
モチベーションマネジメントは、社員のモチベーションを把握することがスタートです。チームミーティングや1on1ミーティングに加えてサーベイを実施することで、より深くモチベーションを把握することができるでしょう。変化の大きい時代を勝ち抜くためにも、社員モチベーションを向上させ、パフォーマンスの最大化に取り組んでいきたいものです。
リアルワン株式会社は、サーベイの専門会社です。第一線の専門家が監修する「従業員満足度調査(ES調査)」「エンゲージメントサーベイ」で、モチベーションマネジメントをサポートします。
社員のモチベーションを把握するために、サーベイの実施を検討される企業様は、リアルワンご相談ください。お問い合わせは、下記リンクから受け付けています。