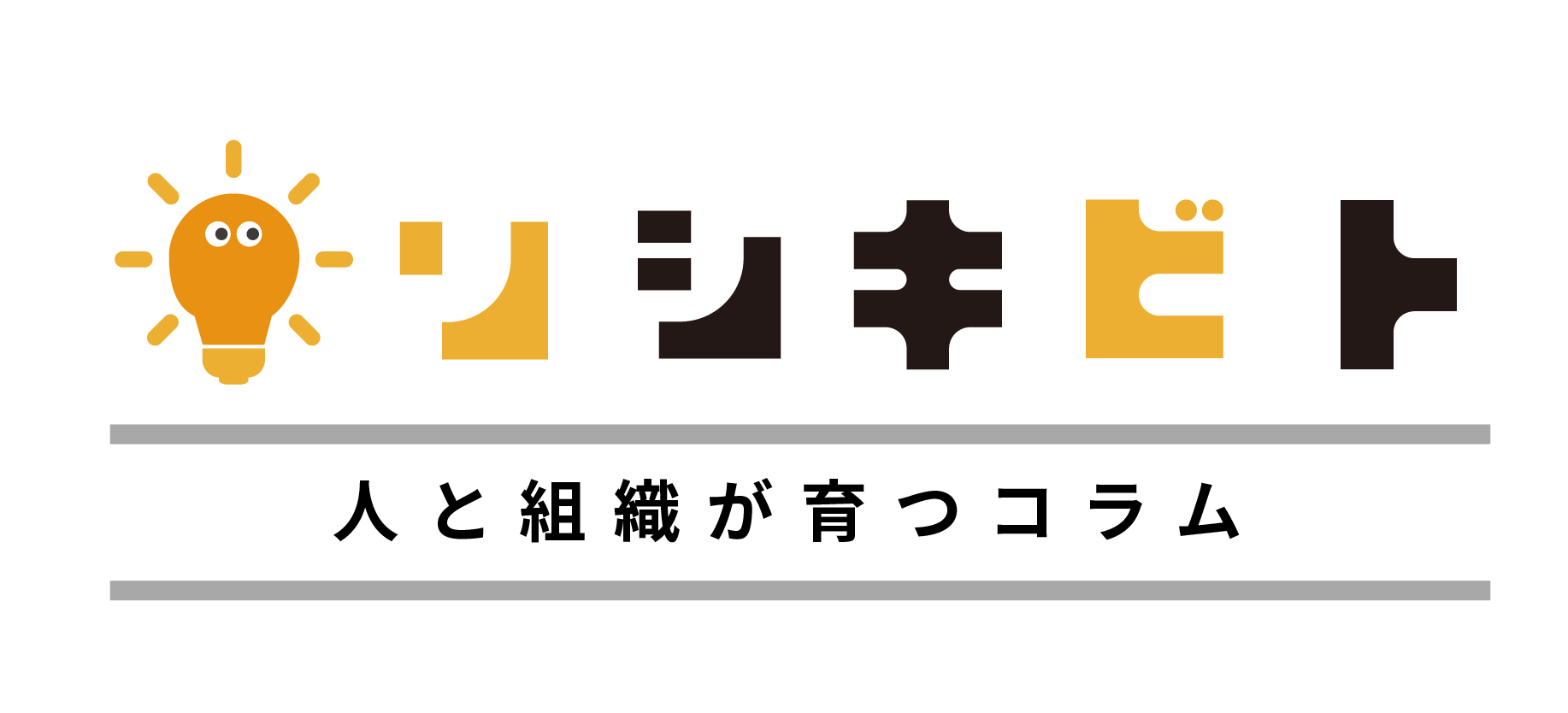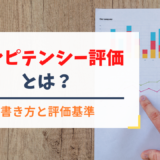モチベーションは組織の創造性や業績を高める重要な要素として考えられています。しかし、仕事内容や価値観の多様化によってモチベーション・マネジメントの難易度が上がり、苦戦している企業は少なくありません。本記事では、モチベーション理論を解説した上で、効果的なモチベーション・マネジメントをご紹介します。
モチベーションが重要な理由

組織の成長と存続は、組織を構成する従業員の行動にかかっていると言っても過言ではありません。そして行動のもととなるのがモチベーション(動機づけ)と言われています。
私たち人間は行動を起こす前に、「その行動は意味があるのか」「その行動は大切なことなのか」などを考え、行動する/行動しないの意思決定をおこないます。正しい動機づけによる行動は、組織を良い方向へ導きます。一方で、正しくない動機づけによる行動は、組織の成長や生産性を低下させるだけではなく、不正などを誘発する恐れがあります。
また、ラウラー氏とポーター氏のMARSモデルでは、組織の競争力につながる創造性や業績の先行条件として以下が挙げられています。
【MARSモデル】
- M:Motivation(モチベーション)
- A:Ability(能力)
- R:Roll Perception(役割認識)
- S:Situational Factors(状況要因)
このモデルでは、個人もチームも、高いモチベーションを持った状態で、自身が持っている知識や能力を、自身の役割を的確に認識した上で効果的に発揮することで、組織は成長できると言われています。また、この一連の流れを実現させるためには、組織文化、制度、リーダーによる働きかけなどの状況要因が関連しているとされています。
そのため、個々人が働くモチベーションについて考えることはもちろん、マネジャー層に至っては、どのように部下のモチベーションを上げるか考える必要があります。
モチベーションの3要素

モチベーションは覚醒、持続性、方向性の3要素で構成されています。それぞれの要素について解説していきます。
モチベーションの要素1:覚醒
人間が行動するためには、その人の意欲が一定の水準以上に「覚醒」していなければなりません。ここでいう覚醒とは、目が開かれ、気持ちが前向きになっている状態を意味します。仕事に対する積極的な姿勢、活発な言動は覚醒している状態としてみなされます。
モチベーションの要素2:持続性
持続性とは、粘り強さや根気強さを指します。せっかく覚醒して行動しても、その意欲や行動が継続しなければ成果を望めません。そのため、持続性も重要な要素であると考えられています。
モチベーションの要素3:方向性
覚醒、持続性がそろっていても、行動の方向性が間違っていると成果につながりません。そのため、モチベーションの3つ目の要素として方向性が挙げられています。とくにミレニアル世代やZ世代は「職場には活気があり、持続的に事業活動ができている。しかし、自社の活動にはどのような意義があるのだろうか」と考える傾向があり、組織の方向性に強い関心を寄せています。
モチベーション理論の変遷
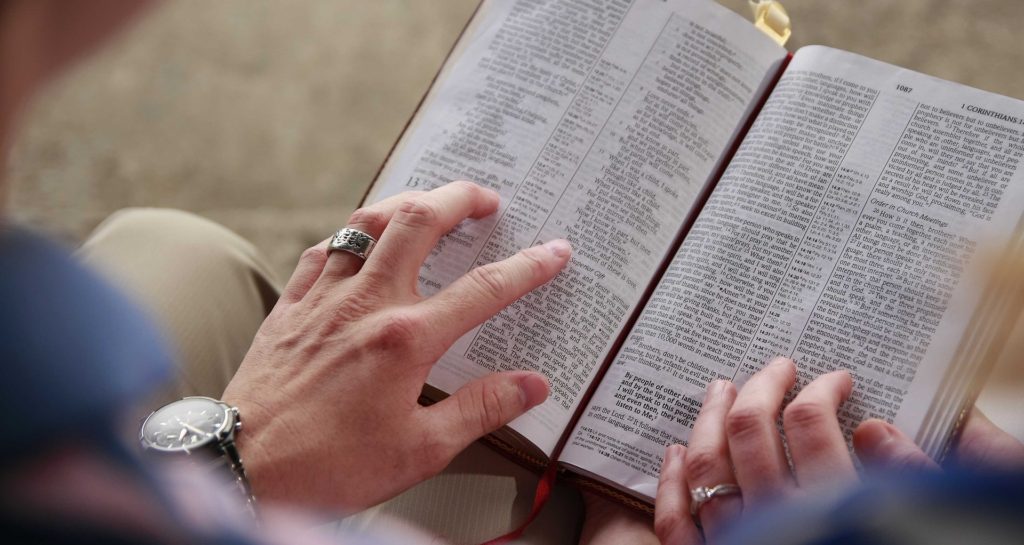
1900年代初頭からモチベーションに関するさまざまな研究がされてきました。ここでは、代表的な理論を解説します。
テーラーの科学的管理法
1911年、フレドリック・テーラー氏は、人は金銭によって動機づけられるとし、科学的管理法を提唱しました。
科学的管理法では、模範的な働きをする従業員の働きぶりと成果を参考に、各業務に対して「標準作業」を設定し、一定の目標やノルマを達成することで賃金を支払う仕組みです。
この仕組みを導入することで、企業側は労働者から安定した成果を得られ、労働者側は努力に応じて高い賃金を得ることができました。この手法は工場などの生産現場の効率化と生産性向上に貢献しました。
メイヨーとレスリスバーガーの人間関係論
1927年、メイヨー氏とレスリスバーガー氏はシカゴのウェスタン・エレクトリック会社のホーソン工場で、どのような環境が生産能率に影響を与えるか調べるために、以下の実験をおこないました。
【ホーソン工場の実験】
- 照明実験(工場の照明と作業能率の関係)
- リレー組み立て実験(条件の変更と作業能率の関係)
- 面接実験(労働者に面接して聞き取り調査)
- バンク配線実験(協業の成果を計測)
さまざまな実験を通じて、物理的な環境や金銭だけではなく、自然発生した人間関係も生産能率に重要な影響を与えることが示唆されました。実験では、共通認識を持って団結しているチーム、リーダーとのメンバーの関係性が良いチームは、生産能率が高かったことが報告されています。
マズローの欲求段階説
アメリカの心理学者のアブラハム・マズロー氏は人間の欲求を5段階に体系化しました。5つの欲求は一番下の段から、生理的欲求、安全の欲求、社会的欲求、自我の欲求、自己実現の欲求です。
【5つの欲求】
※生理的欲求から上に向かって欲求の段階が上がっていく
- 自己実現の欲求:個人の能力や才能を最大限に発揮し、自分自身を実現するための欲求
- 自我の欲求:他者から認められ、尊重されることを求める欲求
- 社会的欲求:愛情、所属意識、友情など、社会的なつながりや関係性を求める欲求
- 安全欲求:身体的危険や脅威から身を守り、安全で保護された環境を求める欲求
- 生理的欲求:衣食住、睡眠、性的欲求などの身体的欲求
マズローの欲求段階説では、これらの欲求は下から順番に満たされていき、低次元の欲求が満たされるとひとつ上の欲求を満たすことを動機とし、人間は行動するとされています。
欲求段階説では、一旦欲求が満たされると、その欲求は動機づけ要因にはならなくなります。しかし、自己実現の欲求だけは満たされることなく、さらに上を目指そうという動機が生まれ続けると考えられています。
アルダファーのERG理論
ERG理論とは、アメリカの心理学者クレイトン・アルダファー氏がマズローの欲求段階説を発展させた理論です。ERG理論では、人間の欲求を「E:Existence(存在)」、「R:Relatedness(関係)」、「G:Growth(成長)」の3カテゴリーに分類しています。
ERG理論は、マズローの欲求段階説とは異なり、下位のカテゴリーが満たされなくても上位のカテゴリーに進むことができるとされています。また、上位のカテゴリーにある成長欲求が強くなると、関係性や存在に関する欲求も再び強くなることがあると考えられています。
【3つのカテゴリー】
※Existence(存在)から上に向かって欲求の段階が上がっていく
- Growth(成長):自己実現や個人の成長に関する欲求。才能や能力を最大限に発揮し、自分自身を実現するための欲求など。
- Relatedness(関係):他者との関係性やコミュニケーションに関する欲求。愛情や所属意識、友情など、社会的なつながりや関係性を求める欲求など。
- Existence(存在):生理的・物質的な欲求や安全保障に関する欲求。食事や住居、収入などの基本的な必需品を得るために働く欲求など。
マグレガーのXY理論
アメリカの心理学者であり経営学者でもあるダグラス・マクレガー氏はXY理論を提唱しました。XY理論とは、人々のモチベーションを「X理論」と「Y理論」の2つに分類する理論です。組織における人々の動機づけに関する理論として、現在でも広く用いられています。
なお、X理論とY理論は対立するものではなく、お互いを補い合うような関係にあります。従業員の状態や経営状況に応じて、X理論とY理論を使い分けることが大切です。
X理論
- 性悪説に基づいた考え方
- 人間は自己中心的で、責任感がなく、楽をすることを好む
- 人間は怠惰であり、強制や命令をされないと働かない
- 人間を働かせるためには、報酬や罰などの外部的刺激が必要
- 人間は安全を望み、命令されることで責任を回避する
Y理論
- 性善説に基づいた考え方
- 人間は自己管理的であり、創造的であり、自発的である
- 人間は強制をしなくても働く
- 人間は自身が設定した目標に対して、自主的に行動する
- 承認欲求や自己実現欲求が満たされる目標に対してモチベーションを高く持つ
ハーズバーグの二要因理論
二要因理論はアメリカの臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグ氏によって提唱されました。職務満足と職務不満足を引き起こす要因は、それぞれ異なる原因によって引き起こされているという考え方です。職務満足は「動機づけ要因」、職務不満足は「衛生要因」が影響しているとされています。
二要因理論では、「動機づけ要因」を高めてモチベーションを向上させ、同時に「衛生要因」を満たして不満足を解消することが重要とされています。例えば、高い給与が支払われていても仕事内容が単調でやり甲斐がない場合、モチベーションは低下し、結果的に仕事に対する不満足感が生じると考えられます。
そのため、ハーズバーグは「職務充実(Job Enrichment)」の必要性を主張しています。職務充実とは、従来の職務に管理的な要素を加え、職務を垂直的・質的に増大させる方策のことです。責任や権限の範囲を広げたり、難易度の高い仕事を任せたりして、やり甲斐を感じさせることを意味します。
| 衛生要因 | 動機づけ要因 |
| 衛生要因が不十分な場合、人々は不満を感じる。 | 動機づけ要因が高い場合、やり甲斐を感じて 自発的に働くことができる。 |
| ・管理、監督の質 ・賃金 ・会社の方針 ・物理的な作業条件 ・対人関係 ・雇用保障 | ・達成 ・個人の成長機会 ・昇進の機会 ・表彰や承認 ・仕事の責任 |
モチベーション・マネジメント

従業員の「能動的」な行動が高い業績や創造性をもたらすことは、先行研究や企業事例によって広く認識されるようになりました。そのため、近年はモチベーションの中でも内発的動機に焦点があてられています。ここでは、モチベーション・マネジメントが難しい理由と成功させるためのポイントをご紹介します。
モチベーションの誘発や維持が難しい理由
従業員の内発的動機が常に誘発され、維持される状況や環境をつくることは容易ではありません。モチベーションの誘発や維持が難しい理由として、心理学者のデシ氏やワイナー氏は下記を挙げています。
【内発的動機の誘発と維持が抑制される理由】
- 組織の活動が必ずしも従業員(個人)がやりたいこと、好きなことと一致していない。
- 従業員視点では、組織から役割や義務を与えられ、指示や依頼を受けて行動することがほとんどである。
- 活動の成果は個人の能力や努力だけではなく、仕事の特性、周囲との協同や関係者からの支援などによって左右されることが多い。
- 成果に運や偶然の要素が介在することがある。
モチベーション・マネジメントを成功させるポイント
内発的動機の誘発や維持がさまざまな理由で抑制されることから、従業員の内発的動機の自然発生を期待するマネジメントは危険であると考えられます。九州大学大学院の教授である古川氏は著書(※)の中で、内発的動機を誘発するためには、以下について意識する必要があると述べています。
- 従業員に対して「なすべきこと」、「期待されていること」を実行するための外発的モチベーションを確実に生み出した上で、内発的モチベーションを誘発する工夫をすること。
- 周りからの働きかけによって、外発的モチベーションを内発的モチベーションに移行させること。
さらに古川氏は、マネジャー層がモチベーション・マネジメントを効果的に実施するためには、「課題の特性」と「課題遂行の段階」を押さえておく必要があるとしています。課題遂行の段階によるモチベーションの源泉は次の図のように整理され、マネジャー層は課題遂行の段階に応じて部下へのアプローチ方法を変える必要があります。
| 着手段階 やってみよう(覚醒と方向性) | 中途段階 やり続けよう(持続) | 完了・結果段階 やってよかった、また次も | |
| メンバーの意識 | ・取り組む課題の意義がわかる ・方法論やシナリオが見える | ・自分の活動の確認 ・進捗や進歩が自覚できる ・手応えを感じる ・解決や達成の糸口が見える ・周囲との協力関係 | ・達成感 ・自己成長感 ・公正感 |
| 周囲の働きかけ | ・課題と役割りを明確にする ・期待や信頼を寄せる ・指示や要請をする | ・関心を寄せ、注目をする ・助言や相談に乗る ・激励や支援をする ・フィードバックをする ・判断や裁量を尊重する | ・労い、感謝をする ・工夫や努力の承認や称賛 ・評価し、報酬を用意する |
従業員のモチベーションを可視化してモチベーション・マネジメントに取り組もう

企業で働く従業員はさまざまな目的や価値観を持っています。そんな中、企業は個人の目的や欲求を充足し、仕事の意欲を高められる制度や環境を整えなければなりません。また、マネジャー層は部下のモチベーションを誘発し、維持させるために働きかける必要があります。
モチベーション・マネジメントには、各種理論や手法のほかに、従業員満足度調査やエンゲージメント調査から得られるデータも役立ちます。これらのツールも活用し、従業員のモチベーションの状態を把握しながらモチベーション・マネジメントに取り組むと良いでしょう。
【参考文献】
- ※ 古川久敬. “組織心理学”. 株式会社培風館, 2011.